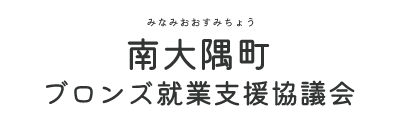地域に移住するうえで不安なのは、やはり「仕事」についてだろう。特に、異業種から転換するならなおさらだ。
仲究(なか・きわむ)さんは、2019年の8月に家族で南大隅に移住し、警察官から農家になった。農業といえば機械や土地など、初期投資が必要な仕事の代表格だ。お子さんもいる中で新たなチャレンジに挑むのは、かなりの勇気が必要だろう。
2022年で就農3年目を迎える仲さんは「地域での新規就農」について、どのように考えているのだろうか?移住までの経緯や就農までの流れを振り返り、新規就農成功のポイントについて一緒に考えてみよう。
インゲンと熱帯果樹の「二刀流」
「警察官時代は、朝の5:30に家を出て夜の22:00に帰って来ることもザラでした。農業では朝は早いかもしれませんが、夕日が沈めば帰れます。大変ですが、『健康的な疲れ』なので大丈夫です」日に焼けた精悍な笑顔で、究さんは語る。

究さんは、奥様の理恵(りえ)さんと娘さんの3人家族だ。インゲン、パインアップル、アボカドの3種類の作物を育てている。「始めは農業をやるつもりはなかったのですが、地元の方々のお話を聞いて『先輩方のお手本があれば、自分でもできるかも』と思えたんです」
パインアップルやアボカドは、南大隅ではここ数年で特産品化が推進されている。理恵さんは「初めて南大隅にきたときに、生のパインアップルの甘さに衝撃を受けました。これはぜひやってみたい、と思いましたね」と笑顔で話す。
しかし「やりたいこと」だけで作物を決定したわけではないのが、仲さんご夫婦の冷静なところだ。「熱帯果樹は、植えてから収穫できるまでに数年かかります。中学生の子供もいる中で、2〜3年無収入になるのはさすがに厳しい。なので、まずは収入が安定しやすいインゲンを作って、それと並行して作りやすい作物としてパインアップルを選んだんです」
実際にどのようなプランで栽培を進めるかは、南大隅町役場の技術指導員の方と相談して決定した。「やりたいこと」は持ちつつ、現実的な部分までしっかり考えて作目を選ぶのは、新規就農の重要なポイントだ。
島の暮らしと子育てと
そんな仲さんご夫婦が移住を考えたきっかけは、警察官時代の小笠原諸島への転勤だった。長らく東京勤務だったが、1年半のあいだ「父島」で生活することになったのだ。「人口がおよそ2000人の島なのですが、住民の多くが移住者なんです。ホエールウォッチング・ドルフィンスイムといった海のインストラクターさんや小規模農家の方など、今までに会ったことがない人たちばかり。こういう生き方もあるんだ、という発見がありました」と感慨深げに話す。
特に子育てについては、大きな刺激を受けた。当時小3だった娘さんは毎日のように友達と海で遊び、真っ黒に日焼けして、裸足で帰ってくる日々。「島民のみなさんはほとんど全員知り合いのような感じで、自分の子供のように娘を見守ってくださいました。田舎でのびのびと子育てができるのは、やはりいいなと実感しましたね」と理恵さんは話す。
その後は東京に戻ったが、理恵さんの中で地域への移住についての思いが強くなっていった。父島は素敵な場所だが、地価や物価が高めで、ずっと暮らしていくのはなかなか難しいと感じた。そこで「移住フェア」に参加したところ、南大隅との出会いがあったのだ。
現地でのコミュニケーションの大切さ
まずは「お試し住宅」で数日間滞在し、役場の担当者や地元の方々のところを周った。「お試し住宅」は、南大隅町役場が管理する一軒家で、移住希望者には格安で貸し出しが行われている。短期滞在用だが、移住を考えるにはぴったりの施設だ。「実際に現場に来てみて、印象が大きく変わりました。実際に子供たちの通学風景を見たり、同世代のお子さんを持つお母さんから学校についての話を聞いたりできたのはよかったですね。現地での生活についてしっかりイメージが持てたので、安心して移住を決められました」と理恵さんは笑顔で話す。
就農してからは、地元の農家から多くのサポートがあった。インゲン栽培に必要なハウスの資材は、先輩農家から譲り受けたものも多い。水道を通す作業やハウスの組み立てにも協力いただき、今でも水やりの仕方などアドバイスをくださるそうだ。「僕たちがインゲンを始めて2年経ちますが、そのあいだに新たにインゲンを始めた農家も2〜3軒出てきました。インゲン部会は後輩の農家に対して気配りしてくださる方が多いので、参入しやすいのかもしれませんね」と究さんは語る。究さん自身も、周りの農家で人手が必要なときはお手伝いに行くそうだ。

「インゲンのいいところは、失敗しても大打撃にはなりにくいところ。100kgの収量が80kgになることはありますが、0kgになることはそうない。まずは一歩踏み出して、やってみることが大事だと思います」とご夫婦は笑顔で顔を見合わせる。
新規就農で大事なのは、まずは現地に赴いてみることだ。地域の先輩方とお話ししてみて、やりたいことと現実を擦り合わせる。そこから地域の方々とのコミュニケーションが生まれ、サポートを受けながら走り出せるようになる。最終的には、自分なりの農業のスタイルが見えてくる。
まずは地域を実際に訪れ、「堅実な冒険」ができるように地図を描く。移住の一歩は、そこから始まるのだ。